-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2026年2月 日 月 火 水 木 金 土 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
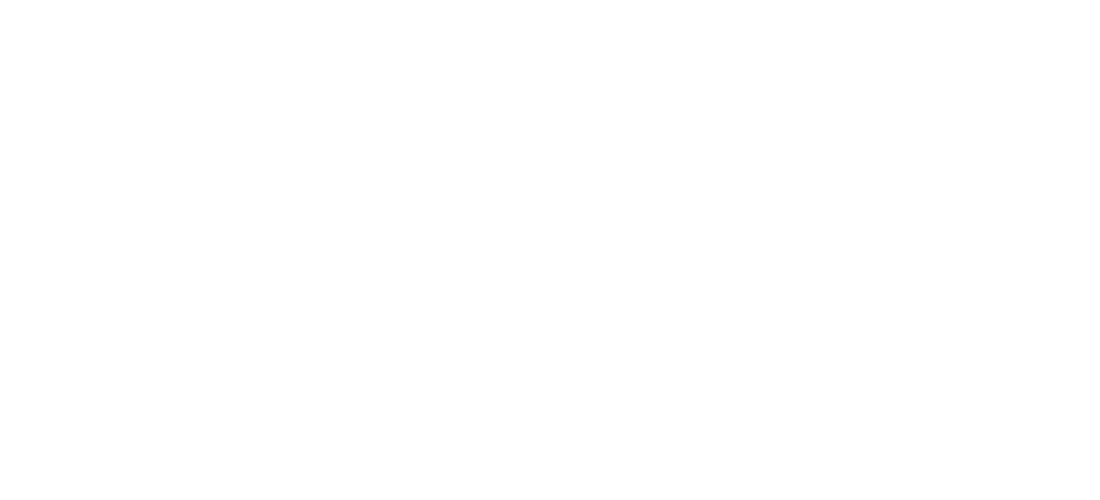
皆さんこんにちは!
株式会社中村瓦の更新担当の中西です!
さて今日は
ということで、今回は、瓦工事における施工前に必ずチェックしておくべき10のポイントを実務視点から徹底的に解説します。
瓦工事は「最後の仕上げ工事の一部」でありながら、
その耐久性・防水性・美観・安全性は、“施工前の事前確認”にかかっていると言っても過言ではありません。
瓦工事には以下のようなやり直しが困難なリスクがつきまといます:
雨漏り(ルーフィング・雨仕舞の不備)
瓦のズレや飛散(緊結不良・風対策不足)
棟崩れや破損(下地補強不足・材料不備)
意匠のバランス崩れ(割付・役物配置ミス)
これらの多くは、実は施工前の「ちょっとした確認不足」から生じているのです。
野地板の厚さ(12mm以上が一般的)・垂木ピッチの確認
湿気や腐食、たわみ、浮きがないか
リフォーム現場では特に下地の劣化を確認
下地の精度が低いと、瓦の浮き・施工不良・瓦割れにつながります。
ルーフィングの種類(アスファルトルーフィング/高耐久タイプ)
重ね幅(最低100mm)、軒先からの施工順序
破れ・シワ・浮き・釘抜けの有無
瓦は“防水材”ではありません。防水の本体はルーフィングです。
最低でも3寸勾配以上が必要(瓦の種類によって異なる)
勾配不足の場合、雨が逆流するリスクあり
緩勾配の屋根には、防災瓦や金具補強を検討
勾配が足りない屋根では、雨漏りや結露、耐風性低下の危険性が高まります。
使用する瓦の品番・形状・色(サンプルと合致しているか)
棟瓦・軒瓦・巴瓦などの役物(やくもの)の数量・納まり確認
防災瓦、軽量瓦など機能面も含めて仕様確認
瓦の種類を間違えると、全体の景観バランスや防災性能に影響します。
平部の割付(端部・谷部の寸法調整・切断の必要性)
棟の構成(のし瓦の段数、冠瓦の配置)
ケラバ・軒先の役物の数と配置順
割付図を用意しないと、現場での勘頼みになり、施工ミスが起こりやすくなります。
釘打ち or ビス止めの有無と本数(全数緊結が主流)
ガイドライン工法に準拠しているか(地域による)
棟部分の南蛮漆喰施工 or 乾式施工の選定
台風・地震の多い日本では、「ただの装飾材」ではなく、構造材としての緊結設計が必要です。
棟芯材(木材・金属製)の寸法と配置位置
鉄筋・補強金物・棟金具の種類と数量
のし瓦積み数に応じた強度計算(特に高棟)
棟の崩壊やひび割れは、事前準備と芯材選定で防げます。
谷板金の材質(ステンレス/ガルバ/銅)と重ね幅
雨仕舞部分(ケラバ・隅棟・軒先)での逆流防止処理
雨樋との高さ・勾配整合
瓦は「雨を受ける」設計ではなく、「雨を流す」設計が必要です。
足場の設置状況(瓦搬入可能か、屋根上作業の安全性)
クレーン車や荷揚げ機の設置場所の確保
瓦荷下ろし時の破損リスクと養生方法
高所作業が主となる瓦工事では、安全設備の確認は最優先事項です。
雨・強風・猛暑・降雪などの施工リスク予測
瓦施工中は、急な雨に備えて防水シートの仮養生を準備
乾燥が必要な工法(漆喰・モルタル)の施工適正気温を確認
天候トラブルは、仕上がり・安全・工程遅延の大きな要因になります。
瓦工事は、施工精度が見た目にも直結する工事です。
だからこそ、準備不足や確認ミスはすぐに表面化し、クレームや事故につながります。
割付のズレ → 見た目が悪い
釘不足 → 台風で瓦が飛ぶ
防水シート破れ → 雨漏り
棟の積み過ぎ → 地震で倒壊
これらすべてを未然に防ぐには、「事前確認の徹底」が最も有効なのです。
日本の建築において、瓦屋根は“文化”と“技術”の象徴です。
その美しさと機能を最大限に活かすには、現場での確認力=職人の判断力とチームの共有力が試されます。
瓦の割付、緊結、納まりの確認
下地、防水、棟の構造チェック
天候、安全、工程の確認
これらを事前に丁寧に確認し、記録・共有することが、
結果として「強く、美しく、長く保つ屋根」につながるのです。
